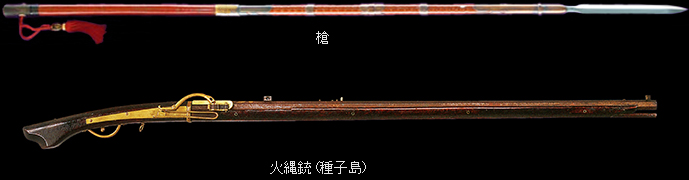
| 日本刀の考察 刀と日本人2 0 |
戦国〜昭和時代 |
| 日本人にとっての日本刀とは | 女性懐剣 | この日本刀と共に | 刀剣の精神 | 刀と日本人 | 軍刀の意義 | ホーム |
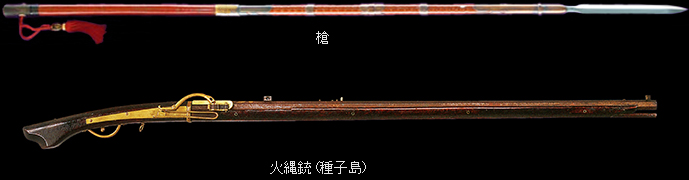
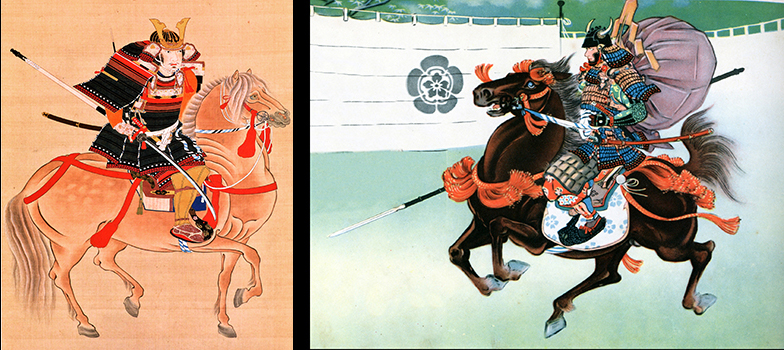

 |
泰平の世に、戦いは遙か遠い記憶の彼方に去っていた。 幕藩体制の中で、武士は「軍事技術者」としての意味を失い、忠実な官吏(文官・行政官)の能力があれば良 かった。 武器であった刀は装身具と化した。刀身にも盛んに彫刻されたが、それは刀の装飾にしか過ぎなかった。 鎌倉武士が太刀に祈った彫刻とは自ずと別のものであった。 拵えも華美を極めた。 拵えに工芸の贅を尽くし、刀身に華麗な彫刻を施し、涛乱刃、富士山の刃文、五の目乱れ、皆焼刃などの華や かな刃文が喜ばれた。刀は「武士の魂」とはほど遠い存在になった。 刀剣の聖性には程遠く、鎌倉の刀剣観からしても、将に堕落以外の何ものでもなかった。 そこには戦国期の武器観も、後鳥羽院の刀剣美学も、古代神話の刀剣信仰も程遠い存在であった。 刀と刀剣観が堕落したのは江戸泰平の中期である。 |
 |
一方、武士の官僚化によって、武士らしい武士像を求める庶民の希求が仇討ち物 の本や演劇を流行らせた。 「仮名手本忠臣蔵」、「道中双六伊賀仇討」は江戸庶民に圧倒的に支持された。 それは現代にも及んでいる。 不条理に物言えぬ弱者の庶民は「勧善懲悪」に喝采した。 武士である主人公の「義・忠・孝」に感銘した。 懲悪物語に日常の鬱積(うっせき)を晴らし溜飲を下げた。 |
 |
日本人の心性を譬えれば、朝日に輝く山桜のようだと説いた。宣長は桜を讃(たた)えた。 何よりも民族の花として桜を宣揚した。 桜が、人の死生観の象徴として譬えにされた。 (この詩の言葉は大戦末期の海軍・神風特別攻撃隊の隊名に使われた )
万葉の桜児※1、
大伴家持の桜歌、八代集※2の桜歌とは異質な桜観の成立だった。桜の新しい観念は、この宣長より始まった。 ※1 乙女の名、二人の男性に愛された為に命を絶った物語 ※2 平安時代中期から鎌倉時代初期にかけて撰集された8つの勅撰和歌集 |
 |
慶應4年(1868)、倒幕の終結は、皮肉にも洋夷を討つ日本刀の時代を終焉 (しゅうえん)させた。 明治新政府は武士階級を解体して帯刀を禁止し、西洋文明の導入を急い だ。これは旧来の日本文化の破壊であった。 洋夷の日本刀で成立した明治新政府が、その日本刀を否定するという誠 に皮肉な、そして倒幕運動に身を投じた武士達にとっては明らかな背信 行為であった。「尊皇攘夷」とは一体何だったのかという疑念に苛(さいな) まれたに違いない。 |

 三笠艦橋の東郷司令長官 |
その後の日清、就中(なかんずく)、
日露戦争で、この「大和魂」が大国相手の劣勢な日本軍を勝利に導 く事になる。 大国ロシアを迎え討つ日本軍将兵達はね血反吐を吐く猛訓練を繰り返した。 旅順口閉塞作戦では決死隊が編成された。将兵達の国を護る一念は死をも超克(ちょうこく)していた。 東郷平八郎海軍大将は、日本海々戦時、海軍長剣「吉房」を左手に握り、砲弾の飛来する露出艦橋 に立って艦隊の指揮を執った。 (三笠艦橋の図と東郷海軍大将参照) 敵艦隊への捨て身の肉迫攻撃である。 艦隊決戦に長剣(軍刀)は無用であった。 然し、近距離砲戦は艦隊の白兵戦である。その為に武士の魂たる日本刀は手放せなかった。 近代戦に長剣を携えた事は、武人としての心意気、洋夷を滅する日本刀を携える事で己の「大和 心」とした。 日本刀を握りしめ、国難に死を賭して立ち向かう武人の姿は国民に深い感銘を与えた。 |
| ← 刀と日本人(1) ホーム 日本刀考 | 女性懐剣 → |